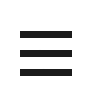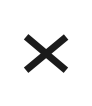良洞村を後にし、次に向かうのは安東(アンドン)市。
こちらは、その市内の外れにある集落「河回村(ハフェマウル)」。
李朝の時代から600年、当時の精舎や書院をはじめ伝統的な住文化が残り、
両班が住み着いた村。今も普通に暮らしている村人たちがいます。
良洞村とともにユネスコ世界文化遺産に登録されています。
村の対岸には「芙蓉台(プヨンデ)」という奇岩絶壁があり、
山々に囲まれつつ、麓には悠々と回わるように流れる大河。
ご察しの通り、S字型に曲がりくねった川に囲まれた立地が名前の由来ですね。
こちらの写真は、その絶壁から村を臨んだ風景です。
この村は、幸いにも壬生乱(豊臣秀吉の侵略)の被害にあわなかったので、
上流から庶民まで、当時の豊かな伝統的な住まいが残っております。
村には180戸ほどの村人が藁ぶき家屋や瓦葺家屋に住んでいるそうです。
家の設えや庭など昔ながらの風景を残しつつも、
パラボラアンテナが立っていることから、
現在も人が住んでいる様子を垣間見ることができます。
美しい街並み。道は舗装されることなく、土のまま。
各住居には土塀が回されているのですが、目線くらいの高さ。
家々の軒が風景として繋がり、適度に曲がりによってアイストップを形成し、
その向こうへ向かう期待感を高めつつ、奥行きを感じる構成が多見されます。
迷路のようでもありますが、すごく空間が豊かで、
実際よりも大きな村であるかのような錯覚を感じます。
村の中心に位置する樹齢600年を越えるケヤキ。
村の守護樹「三神堂御神木」として祀られています。
子を授け、出産と成長を助けると伝えられているそうです。
この村を代表する柳雲龍の故宅「養真堂(ヤンジンダン)」。
安東村は、豊山柳氏の一族によって作られた村だそうで、こちらはその総本家。
オンドルのための基壇を作り、その上に重厚な家屋が載っています。
立嚴古宅という扁額が掛かった棟が舎廊棟(サランチェ/息子主人の居室や接客の場)、右手には母屋(アンチェ/女性が暮らす空間)を遮るように行廊棟(ヘランチェ:下人や作業具の部屋が並ぶ棟)が配置され、儒教の厳格な男女の区別が、住まいの配置や設えにも明確に表れています。
家づくり学校修学旅行でのお話です。来期受講生募集中。お早めに。コチラ≫
以下、目に留まった建築ディテールを2点ほど。