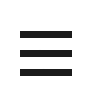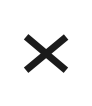12月15日(土)家づくり学校2年生の7回目『瓦』の授業がありました。
行き先は、群馬県西部。引率講師は家づくりの会の徳井正樹先生、
世話役は屋根舞台の小林保さんです。
まず向かったのは『富岡商工会議所』。2018年4月竣工、設計は手塚建築研究所。
内部は菱形の木軸で組まれた斬新な空間なのですが、屋根には瓦が葺かれ、街並みと調和しています。隣には白い蔵。旧呉服問屋の袖蔵をリノベーションし、ギャラリーとして商工会議所と一体的に活用。立派な鬼瓦と棟瓦の意匠が粋。
新築の商工会議所の方は近代的な瓦、蔵リノベの方は近代的な瓦をだるま窯に入れて一手間加えた瓦。その両方を横並びに見れたのは良い機会でした。
続いて『富岡製糸場』。言わずと知れたと世界遺産&国宝。
明治5年創業、棟長100m超の木骨煉瓦造も魅力なのですが、今回の目的は瓦。
現在、西置繭所が改修中。幸いなことに、その様子を間近で見ることが出来ます。
その屋根の改修に当たっているのが、今回の勉強会の世話役・小林さんたち。
文化財というのは、伝統を残す意義もありますゆえ、
その技術が不合理であっても、守らねばなりません。
それゆえの難しい側面もあるようですが、学ぶことも多く、
そんな生のお声を聞く機会に恵まれました。
街中を歩いていると、瓦屋根の街並みが沢山残っています。
瓦屋根が連なっていると、統一感があるように見えますが、
葺かれている時代や職人さんによって、その技術は違います。
棟瓦をはじめ、ところどころに職人さんの個性が発揮され、
粋な世界観を感じることができます。
現代的な瓦は近代設備の整った大きな工場で焼かれ、その仕上がりは均一です。
それは凄い技術で、焼物技術のある到達点なのかもしれませんが、
逆に不均一な方に魅力を感じるという矛盾した心理。
表層的に素材を統一するだけでは生まれない得ない日本の美しい街並み。
場所を甘楽郡甘楽町に移して『Gallery 瓦窯』。
こちらでは、瓦の製造小史を学びます。
甘楽町を拠点とした「新屋根開拓集団 屋根舞台(2000年結成)」という瓦職人と建築家で構成する集団があります。
日本の伝統的な素材である瓦を、現代の住まいや暮らしの中に取り入れて行こう、
と提案している集団なのですが、その瓦産業の歴史を伝えるギャラリーです。

トロッコに乗って、内部を見学。
群馬県西部は、藤岡瓦で知られる瓦の産地。
富岡製糸場が出来た明治時代に飛躍しましたが、
戦後は量産瓦に押され、窯の火は消えて行ったそうです。
その3代目、4代目が、いま熱い思いを持って立ち上がっています。