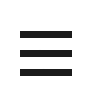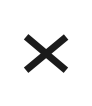桂離宮の見学後『慈照院』も行ってきました。
慈照寺(つまり銀閣寺)ではなく、慈照院です。鞍馬口にある相国寺の塔頭寺院。相国寺には16の塔頭があり、金閣寺や銀閣寺も相国寺の境外塔頭なんだそうです。その銀閣寺を建てた八代将軍・足利義政や桂宮家の菩提所。客殿(本堂)には桂宮家代々の位牌が祀られているという由緒ある寺院なのです。
こちらのお寺の書院「棲碧軒」は、桂宮家の御学問所として建てられたもの。腰高障子や欄間などは、桂離宮「古書院」と同じ材や技法で造られているそうです。桂離宮はもちろん内部に上がることはできないのですが、こちらは上がって近くで見ることができます。ちなみに棲碧軒の内部は写真撮影禁止です。
犬走に貼られた亀甲模様の敷瓦が美しい。御影石の縁石を挟んで、その敷瓦(外部)と墨入りモルタル(内部)の様子。墨入りモルタルは、左官技法のひとつ。さらに磨きという技法で仕上げらているので、艶が出ていて美しい。
こちらの寺院は6年ぶりに特別公開されています。3月18日まで。当院第七世の仏性本源国師と千宗旦(利休の孫)との合作という茶室「頤神室(いしんしつ)」が見れなかったのは残念。
実は一番魅入ってしまったのは、周囲を巡っている築地塀。泥土を突き固めて作った壁なのですが、注目するのは五本の白漆喰の線。眼鏡五線という左官技法で、手間が掛かるもの。本数はお寺の格式を表し、五本は最上位。古いお寺の塀としては珍しいものではありませんが、新しいものは滅多に見られなくなってしまいました。
右手の茶色い壁は昔のもの。青と赤の壁は最近のもの。三色とも品のある美しい色。ユニークかつモダンですね。色違いが並んで見れる所は、そうそうないと思います。
眼鏡五線を知った経緯はコチラ≫ 京都の親方・山本忠和さんのお仕事かもしれませんね。ちなみに家づくり学校の左官授業でお世話になっている古川元章さんのお師匠さんでもあります。古川さんのお話はコチラ≫ 家づくり学校についてはコチラ≫